早期退職という選択肢を考えている方にとって、最も重要な準備の一つが「生活防衛資金」の確保です。会社を辞めて新しい人生のステージに進むことは、大きな希望とともに、同時に経済的なリスクも伴います。十分な準備なく早期退職に踏み切ってしまうと、理想の生活を実現するどころか、経済的な不安に苦しむことになりかねません。
早期退職後の生活は、会社員時代とは全く異なります。毎月決まった給料が入ってこない不安、予想外の出費、社会保険料の負担増など、様々な課題に直面します。こうした状況でも安心して生活できるよう、退職前に必ず確保しておくべきなのが生活防衛資金なのです。
早期退職における生活防衛資金の重要性
会社員として働いている間は、毎月安定した収入があり、健康保険や厚生年金も会社が半分負担してくれています。しかし、早期退職後はこの安定した基盤が一気に失われます。
まず、収入の問題があります。再就職や起業、フリーランスとしての活動を計画している場合でも、すぐに安定した収入が得られるとは限りません。再就職活動には数ヶ月かかることも珍しくありませんし、起業やフリーランスの場合、軌道に乗るまで半年から1年以上かかることもあります。この空白期間を乗り切るための資金が必要です。
次に、社会保険料の負担増があります。会社員時代は健康保険料や厚生年金保険料の半分を会社が負担していましたが、退職後は全額自己負担となります。国民健康保険と国民年金に切り替えた場合、月額3万円から5万円程度の支出増加は覚悟しなければなりません。
さらに、住民税の問題もあります。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職した年の翌年も、会社員時代の収入に基づいた住民税を支払う必要があります。収入がない、または大幅に減少している状況で、数十万円の住民税を納付することになるため、これも大きな負担となります。
また、マイホームの方は外壁塗装など自宅の修繕、あるいは給湯設備の入れ替えなどのタイミングがやってくる可能性もあります。こういう出費もきちんと考慮に入れておくべきです。
また、早期退職後は予想外の出費も増える傾向があります。時間ができたことで旅行や趣味に費用を使いたくなったり、健康診断や人間ドックなど、会社で受けていた福利厚生がなくなることで自己負担が増えたりします。こうした様々な要因により、想定以上に支出が増えることは珍しくありません。
早期退職者が確保すべき生活防衛資金の額
一般的な生活防衛資金は月々の生活費の3ヶ月から6ヶ月分とされていますが、早期退職を計画している方の場合、最低でも1年分、できれば2年から3年分の生活費を確保しておくことが望ましいでしょう。「ロードマップ」の記事でも3か月~6か月分と記載していますが、こちらはあくまでも生活費に充てるお金が確保できている場合にそれを除いて、という意味ですのでご留意ください。
この金額を算出するためには、まず退職後の月々の生活費を正確に見積もる必要があります。会社員時代の生活費に加えて、以下の項目を考慮しましょう。

国民健康保険料と国民年金保険料として月額3万円から5万円、住民税は年間の総額を12で割って月額換算します。例えば年間24万円の住民税であれば、月額2万円を加算します。また、会社の福利厚生で利用していたサービスの自己負担分や、通勤定期券がなくなることによる交通費の増加なども忘れずに計上しましょう。
例えば、月々の基本生活費が25万円の場合、社会保険料4万円、住民税2万円を加えると、退職後の実質的な月額支出は31万円となります。これを2年分確保するとなれば、744万円という金額になります。
「そんなに大金を貯められない」と感じるかもしれませんが、これは早期退職を安全に実行するための現実的な数字です。もし十分な資金がない状態で退職してしまうと、経済的な不安から焦って不本意な仕事に就いたり、理想としていた生活を送れなくなったりする可能性が高くなります。
退職金や確定拠出年金の受け取りがある場合は、それらも生活防衛資金の一部として計算できますが、すぐに現金化できない場合もあるため、注意が必要です。また、iDeCoなどは60歳まで引き出せないため、生活防衛資金には含めないようにしましょう。
早期退職前の生活防衛資金の貯め方
早期退職を数年後に控えている場合、今から計画的に生活防衛資金を貯めていく必要があります。退職までの期間を逆算し、毎月どれくらいの貯蓄が必要かを計算しましょう。
例えば、3年後に早期退職を予定しており、700万円の生活防衛資金が必要な場合、現在の貯蓄が200万円あれば、残り500万円を36ヶ月で貯める必要があります。月額約14万円の貯蓄が必要という計算になります。
この金額を捻出するためには、収入を増やすか支出を減らすか、あるいはその両方を実行する必要があります。まず固定費の徹底的な見直しを行いましょう。早期退職を目指す段階で、すでに生活費を最小化しておくことは、退職後の生活設計にも役立ちます。こちらの記事を参考にしてください。(「家計の把握と最適化」)
携帯電話料金、サブスクリプションサービス、保険料、光熱費など、あらゆる固定費を見直し、月々3万円から5万円程度の削減を目指しましょう。また、外食費や娯楽費なども、早期退職という目標のために一時的に我慢することも必要です。
収入増加の手段としては、残業や休日出勤を増やす方法もありますが、健康を損なっては意味がありません。むしろ、副業を始めることをおすすめします。副業は収入増加だけでなく、退職後の収入源としても活用できる可能性があります。週末起業やクラウドソーシングなど、本業に支障をきたさない範囲で取り組めるものを選びましょう。
ボーナスは全額貯蓄に回すくらいの覚悟が必要です。年2回のボーナスが各50万円であれば、年間100万円を貯蓄できます。これだけで3年間で300万円を確保できる計算になります。
また、生活費の口座と生活防衛資金の口座を完全に分離し、給料日に自動振替で貯蓄用口座に入金するようシステム化しておくことで、確実に資金を積み立てることができます。
早期退職後の収入確保と生活防衛資金の補填
理想的には、早期退職後もできるだけ早く何らかの収入を確保し、生活防衛資金の取り崩しを最小限に抑えることが望ましいです。あるいは、少額でも収入があれば、生活防衛資金の減少スピードを緩やかにできます。
再就職を考える場合、正社員にこだわらず、パートやアルバイト、契約社員なども選択肢に入れましょう。月10万円の収入があれば、年間120万円の生活防衛資金の延命効果があります
フリーランスや起業を目指す場合は、退職前から準備を始め、できれば退職前に小規模でも実績を作っておくことが重要です。退職後すぐに収入がゼロという状態は避けられるよう、計画的に動きましょう。
「副収入減の確保」についてはこちらの記事も参考にしてください。
また、不用品の売却、スキルを活かした副業、投資収益(配当金や家賃収入など、元本を毀損しないもの)なども、生活費の補填に活用できます。ただし、これらはあくまで補助的な収入源と考え、生活の基盤を支えるものとは考えないようにしましょう。
生活防衛資金を使った分については、収入が安定してきたら少しずつでも補填していくことが理想です。完全に枯渇させてしまうと、再び不測の事態が発生した時に対応できなくなります。
まとめ ~ 早期退職成功のカギは準備にあり
早期退職は、人生の新しいステージへの挑戦であり、大きな可能性を秘めています。しかし、その成功のカギは徹底した経済的準備にあります。特に生活防衛資金の確保は、早期退職を実現し、その後の生活を安定させるための最重要事項です。
最低でも1年分、できれば2年から3年分の生活費を確保してから退職することで、焦らず自分のペースで次のステップを踏み出すことができます。この資金があれば、理想の仕事を見つけるまでじっくり時間をかけたり、新しいスキルを習得したり、起業の準備を万全にしたりすることが可能になります。
逆に、十分な準備なく早期退職してしまうと、経済的な不安から本来の目的を見失い、結局は不本意な選択を強いられることになりかねません。早期退職という人生の重要な決断を成功させるために、今日から計画的に生活防衛資金の確保に取り組みましょう。
あなたの早期退職が、経済的な安心と精神的な余裕に支えられた、充実した新しい人生のスタートとなることを願っています。
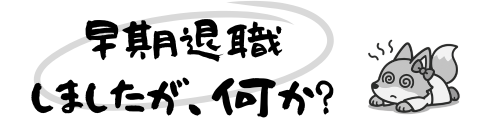
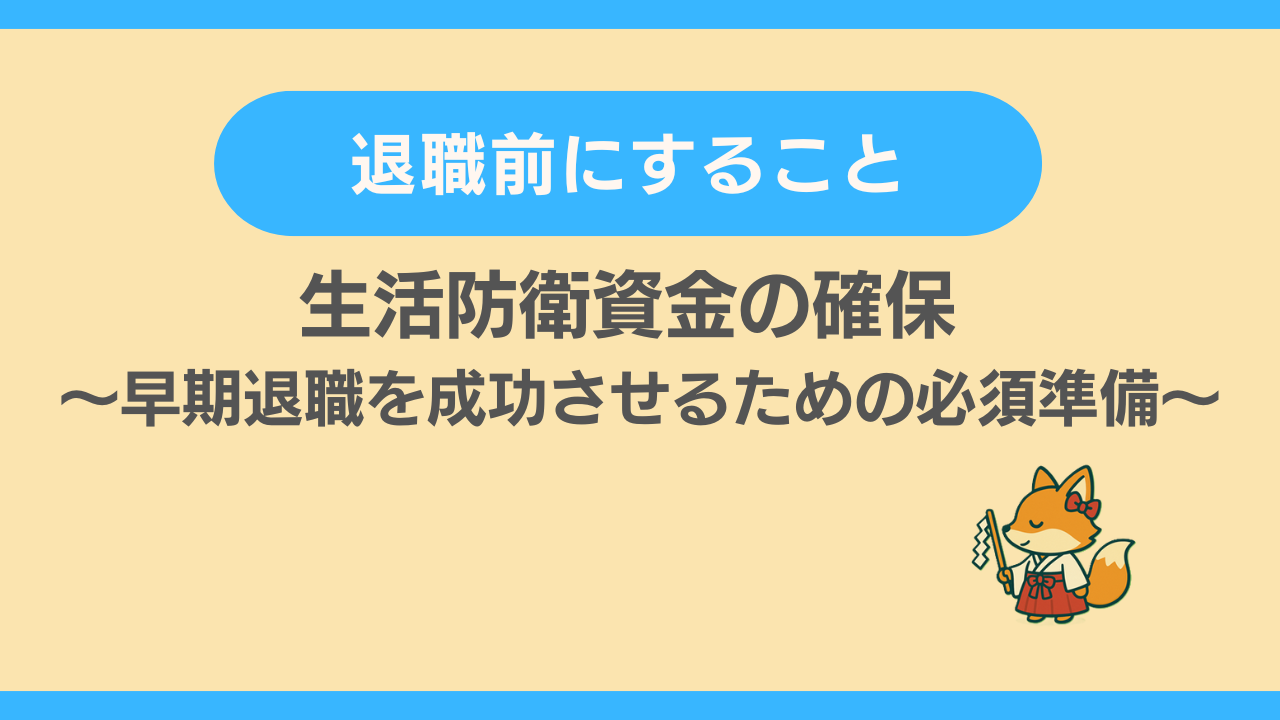
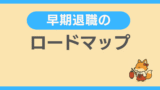
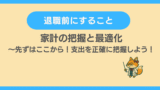
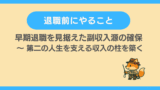
コメント