早期退職を決断された方の多くが直面する重要な手続きの一つが、企業型確定拠出年金(企業型DC)の取り扱いです。会社員時代に積み立ててきた年金資産をどうするのか、この選択は将来の老後資金に大きな影響を与えます。
結論から言えば、ほとんどの場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が最適な選択となります。本記事では、企業型DCからiDeCoへの移換手続きと、早期退職者がiDeCoを最大限活用する方法について詳しく解説します。
企業型DCを放置してはいけない理由
早期退職後、企業型DCをそのまま放置することは避けるべきです。なぜなら、退職後6ヶ月以内に移換手続きを行わないと、自動的に「国民年金基金連合会」に資産が移管され、「自動移換」という状態になってしまうからです。
自動移換になると、様々なデメリットが発生します。まず、毎月の管理手数料が差し引かれ続けるため、資産が目減りしていきます。さらに、運用されないため運用益も得られません。加えて、自動移換されていた期間は確定拠出年金の加入期間としてカウントされないため、将来の受給開始年齢が遅れる可能性もあります。
そして最も問題なのは、自動移換された資産を引き出すには、再度移換手続きと追加の手数料が必要になることです。このような無駄を避けるためにも、退職後は速やかにiDeCoへの移換手続きを行うべきなのです。
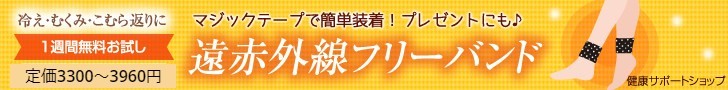
企業型DCからiDeCoへの移換手続き
移換手続きは、思っているよりも簡単です。以下の手順で進めていきましょう。
ステップ1:iDeCoの運営管理機関を選ぶ
まず、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)を選びます。銀行、証券会社、保険会社など、多くの金融機関がiDeCoのサービスを提供しています。
選択のポイントは、口座管理手数料、運用商品のラインナップ、サポート体制の3つです。口座管理手数料は金融機関によって異なり、無料のところもあれば月数百円かかるところもあります。長期間にわたって積み重なるため、できるだけ手数料の安い金融機関を選ぶことをお勧めします。
運用商品については、投資信託の種類や信託報酬の水準を確認しましょう。特に、低コストのインデックスファンドが充実している金融機関が望ましいです。ネット証券系の金融機関は、一般的に手数料が安く、商品ラインナップも充実している傾向があります。ちなみに私は楽天証券を選択しました。客観的に見ても楽天証券が一番のお薦めかなと思います。
ステップ2:iDeCoの加入申込
選んだ金融機関のウェブサイトから資料請求を行ってiDeCoの加入申込書を入手します。すでに証券口座を持っていて、その金融機関で加入申し込みをするならばそれが一番簡単です。この場合、各金融機関のウェブサイトでそのガイダンス通りに手続きを進めていくだけです。概ね個人情報、基礎年金番号、掛金額、運用商品の選択などを記入します。
早期退職者の場合、加入区分は「第1号被保険者」(国民年金加入者)または「第2号被保険者」(厚生年金加入者、再就職した場合)となります。配偶者の扶養に入った場合は「第3号被保険者」です。
ステップ3:企業型DCの資産移換手続き
iDeCoの加入手続きと同時に、企業型DCからの資産移換手続きも行います。多くの場合、「個人別管理資産移換依頼書」という書類が必要になります。この書類は、iDeCoの加入申込書とセットで送られてくることが一般的です。
企業型DCを管理していた記録関連運営管理機関(レコードキーパー)から退職後に「確定拠出年金加入者資格喪失手続完了通知書」がまず送られてきます。概ね退職後1~2週間で来ると思います。この書類到着後すみやかに移換手続きを行うのがよいでしょう。
ステップ4:審査と資産移換
申込書を提出すると、国民年金基金連合会による審査が行われます。審査には通常1〜2ヶ月程度かかります。審査が通過すると、企業型DCの資産が現金化され、iDeCoの口座に移換されます。
金融機関のウェブサイトでiDeCo加入手続きと移換手続きを行った場合、進捗状況も確認することができます。
審査中なのか審査が完了したのか今のステイタスをウェブで確認できますので便利です。
移換手続きが完了すると「確定拠出年金【移換金】お振込み報告書」が届きます。これは移管する資産の生産金額の明細が記載されています。
その後「口座開設のお知らせ」と「インターネットパスワードの通知書」が届きます。
「口座開設のお知らせには加入者口座番号が記載されています。これは金融機関のウェブサイト上でも確認できます。そこから個人アカウントに入るのに「インターネットパスワード」が必要になるので通知書はなくさないように保管してください。
最後に「個人型年金加入確認通知書」が国民年金基金連合会から送られてきます。
移換完了後、改めて運用商品を選択する必要があります。移換時には一旦すべて現金化されているため、放置すると定期預金などの元本確保型商品に自動的に配分される場合があります。必ず自分で運用商品を選択し直しましょう。
注意事項:マッチング拠出はあらかじめ停止を
なかには企業型DCに加入している期間中で「マッチング拠出」をしている方がいると思います。
「マッチング拠出」とは企業型DCで企業が拠出している掛金と同額を上限にして個人でもDCの掛金に上乗せできる制度のことです。こうすれば個人的にも掛金を増やしてDCの運用額を増やすことができますので。
しかしマッチング拠出をしている場合はiDeCo口座を開設することができません。なぜならば制度がかぶっているからです。個人で掛金を拠出して年金資産を運用している、しかも掛金は所得控除ができます。要するにiDeCoと同じなので二重に口座は作れませんよということです。したがってiDeCoに加入する場合はマッチング拠出は停止しておく必要があります。
もしマッチング拠出をしている状態でiDeCo口座を申し込むと審査で不適格となります。1か月ぐらい審査結果を待って、不適格の通知をもらってからマッチングを止めてもう一度申請しなおす、となるとかなり時間のロスになりますので、そうならないように注意が必要です。

iDeCoの掛金設定 – 早期退職者の戦略
iDeCoへの移換が完了したら、次に考えるべきは掛金の設定です。早期退職者の場合、収入状況や今後のライフプランに応じて、戦略的に掛金額を決める必要があります。

掛金の上限額
iDeCoの掛金上限額は、加入区分によって異なります。国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の場合は月額68,000円、第2号被保険者で企業年金がない場合は月額23,000円、企業年金がある場合は月額12,000円または20,000円、第3号被保険者(専業主婦・主夫)の場合は月額23,000円です。
早期退職後、再就職せずに国民年金に加入している場合は、月額68,000円という高い上限を活用できるメリットがあります。
掛金額の決め方
掛金額を決める際は、生活費とのバランスを考えることが重要です。iDeCoは原則として60歳まで引き出せないため、生活防衛資金や日常生活費を確保した上で、余裕資金から拠出するようにしましょう。
収入が不安定な場合は、最低額(月5,000円)から始めて、収入が安定してきたら増額するという方法もあります。iDeCoの掛金は年1回まで変更できるため、状況に応じて柔軟に調整できます。
また、掛金の拠出を一時停止することも可能です。「運用指図者」という立場になることで、新規の拠出を止めつつ、既存の資産を運用し続けることができます。これは、収入が一時的に途絶えた場合などに有効な選択肢です。
税制優遇のメリットを最大化
iDeCoの最大のメリットは、税制優遇です。掛金全額が所得控除の対象となるため、所得税と住民税が軽減されます。ただし、早期退職後で所得がない、または少ない場合は、この控除のメリットを十分に享受できないことに注意が必要です。
例えば、早期退職後に個人事業主として活動し、ある程度の所得がある場合は、iDeCoの掛金を増やすことで節税効果が得られます。一方、無収入または低収入の場合は、無理に高額の掛金を設定する必要はありません。
iDeCoの運用戦略 – 早期退職者が考えるべきこと
早期退職者のiDeCo運用は、一般的な現役世代とは異なる視点が必要です。
運用期間の考慮
早期退職者の場合、60歳までの運用期間が通常の退職者よりも短い可能性があります。例えば、55歳で早期退職した場合、運用期間は5年程度です。一方、45歳で早期退職した場合は15年あります。
運用期間が短い場合は、リスクの高い商品への集中投資は避け、バランス型のポートフォリオを組むことが賢明です。運用期間が長い場合は、株式型投資信託の比率を高めることで、長期的な資産成長を狙うこともできます。
年齢に応じたアセットアロケーション
一般的には、年齢が上がるにつれて、株式などのリスク資産の比率を下げ、債券や定期預金などの安定資産の比率を上げていくことが推奨されます。「100マイナス年齢」が株式の適正比率という目安もあります。
例えば、50歳であれば株式50パーセント、債券・定期預金50パーセントといった配分です。ただし、これはあくまで目安であり、個人のリスク許容度や他の資産状況によって調整すべきです。
リバランスの重要性
一度設定した運用商品の配分は、市場の変動によって徐々にバランスが崩れていきます。定期的(年1回程度)にリバランスを行い、当初の資産配分に戻すことで、リスクをコントロールできます。
iDeCoでは、リバランスの際の売買手数料がかからないため、積極的に活用すべきです。
iDeCoの受給方法と早期退職者の選択肢
iDeCoは、60歳以降に受け取ることができます。ただし、60歳時点で加入期間が10年未満の場合は、受給開始年齢が遅れます。
受給方法は3つあります。一時金として一括で受け取る方法、年金として分割で受け取る方法、そして一時金と年金を組み合わせる方法です。
一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、年金で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。それぞれ税制上のメリットがあるため、退職金や他の年金収入との兼ね合いを考えて、最も有利な方法を選択しましょう。
早期退職の場合、退職金を既に受け取っているケースが多いため、退職所得控除の枠をどれだけ使っているかを確認することが重要です。

よくある質問と注意点
移換手続きを忘れた場合
6ヶ月を過ぎて自動移換されてしまった場合でも、その後にiDeCoに加入して資産を移すことは可能です。ただし、追加の手数料がかかるため、できるだけ早く手続きを行いましょう。
複数の企業型DCがある場合
転職経験がある場合、複数の企業型DCの資産が残っている可能性があります。これらは一つのiDeCo口座にまとめることができます。
海外移住する場合
海外に移住する場合、iDeCoの継続には制限があります。事前に運営管理機関に相談し、適切な手続きを行う必要があります。
まとめ – 早期退職成功のカギはiDeCo活用にあり
企業型DCからiDeCoへの移換は、早期退職後に必ず行うべき重要な手続きです。放置すると資産が目減りするだけでなく、将来の年金受給にも悪影響を及ぼします。
早期退職者は定年まで会社に勤続する人に比べると厚生年金保険料の拠出期間が少なるなるので年金受給額も少なくなるはずです。この部分はiDeCoでしっかり補填する必要があると思います。
iDeCoは税制優遇、運用益非課税、受給時の控除など、多くのメリットがある制度です。早期退職者こそ、この制度を最大限活用し、老後資金の確保と資産運用を同時に進めるべきです。
退職後は様々な手続きに追われますが、iDeCoの移換手続きは結構時間がかかるので優先順位を高く設定し、早めに完了させるべきです。適切な運用と計画的な資産形成により、豊かな老後生活を実現することができるはずです。
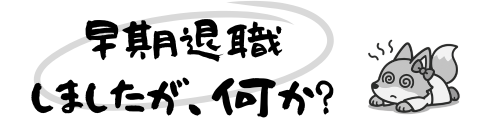
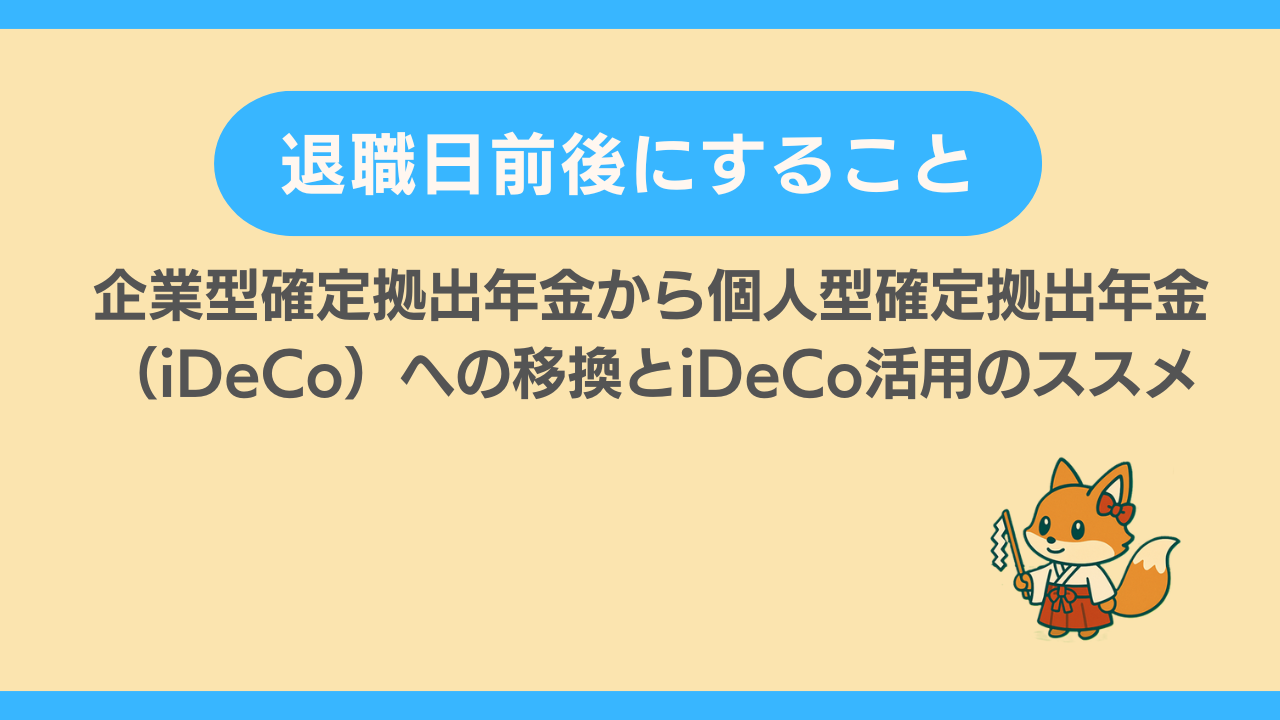
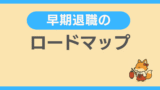
コメント