『ヒストリエ』はあの『寄生獣』の作者岩明均さんの作による歴史漫画です。「月刊アフタヌーン」で2003年から連載されています。現在もまだ継続中なのですが、長期間休載になっています。
本作は作者の岩明均さんがデビュー前から構想を温めていたという作品ですので、おそらくはご本人の中ではもはやライフワーク的な位置づけで作品に取り組んでいらっしゃると見ております。そういう意味では完全な形で完結までもっていってほしい作品のひとつであり、現時点でもまだ続きを非常に楽しみに待っている作品です。
作家:岩明均の作品
岩明均さんの代表作といえば、誰もが知るあの『寄生獣』です。この作品は皆さん同様に私も大好きな作品で、私が考えるベスト作品のベスト5に入る名作です。また別の記事でこの作品にも触れたいと思っています。
実は私が初めて岩明均さんの作品に触れたのは最初の連載作品の『風子のいる店』という作品でした。わたしはこの作品が好きで、単行本も揃えていたんですが、ただ当時は多分それほど人気があった作品ではなかったと思います。絵もそれほどきれいではなかったし、内容も地味な感じでした。
吃音のせいで、対人関係がうまくいかずコンプレックスを抱える女子高生の風子が喫茶店でウェイトレスのバイトをするのですが、その店を舞台に繰り広げられる人間ドラマ、という作品でした。暗いテーマなどもありましたが、読後感がよく、すごくいい作家さんだなと感じておりました。なので『寄生獣』で大ブレイクしたときは、なんとなくすごくうれしかったことを覚えています。
ちなみにこの『風子のいる店』もう絶版になっているようで、楽天で単行本4巻セットの値段を見てびっくりしました。こんな価格になるんやったら処分せずにずっと置いておけばよかった。。。
その他寄生獣の後で発表した「七夕の国」もかなり興味深い設定でよい作品です。他に短編集もいろいろありますが、どの作品もなんとなく岩明さん独特のテンポというか空気感があって、おそらく好みはあるのでしょうが、私にとってはすごく好きな作風です。
「ヒストリエ」の話に戻りますが、そんな岩明均先生が満を持して世に送り出したこの作品は、古代ギリシアという壮大な舞台で繰り広げられる、一人の天才の生涯を描いた歴史大作です。この「ヒストリエ」の持つ多彩な魅力についてご紹介していきたいと思います。
実在の人物である主人公「エウメネス」
紀元前4世紀の古代ギリシア世界を舞台に、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた書記官・エウメネスの波乱の生涯を描いています。エウメネスはアッリアノスの『アレクサンドロス東征記』などにも登場する実在の人物です。
史実では、エウメネスは「書記官」として記録されているものの、その詳細な生い立ちや若き日の活動については史料がほとんど残っていません。岩明均は、この「空白」を逆手に取り、史実の骨格を保ちながら、エウメネスがなぜアレクサンドロス大王の側近となったのか、どのような経験を経てその地位に至ったのかを、緻密な時代考証と豊かな想像力で描き出しています。
主人公エウメネスは、ギリシア世界の都市国家カルディアの名門に生まれ、幼い頃から学問や武術に秀でた少年として描かれます。しかし、ある日突然、彼の出生の秘密が暴かれ、奴隷として転落するという衝撃の展開を迎えます。後に自分を奴隷の身分に落とし、父(育ての親)であるヒエロニュモスを陰謀によって殺害し、まんまとその地位に就いたヘカタイオスとも再会するのですが、特に彼に復讐をするわけでもなく、淡々と接するところも興味深いです。カルディアで自分を拾ってくれたフィリッポス2世(その時は商人アンティゴノスと名乗っていた)にも「おまえばわざわざ復讐のためにこの町に来たんだって?くだらんぞ、そんなことは」といわれて、「だから違うって」と否定しています。
実際に奴隷に落とされたとはいえ、奴隷としてカルディアから黒海沿岸のオルビアに向かう旅の途中で奴隷たちが主人に対して反乱を起こし主人を殺してしまい、その後すぐに船は難破してしまったために、奴隷として過ごすことはほとんどなく、あっけなく自由の身になっています。
その後の少年時代をパフラゴニアにあるボアの村というところで過ごし、いろいろあって村を出ることになり、カルディアに帰ることになるのですが、話の始まりはこのカルディアへの帰途のシーンから始まり、少年時代の回想を経て、再びその時系列に戻る、という形で進行します。
この劇的な転落から始まる物語は、読者を一気に作品世界へと引き込みます。名門の御曹司から一転して奴隷へ、そして再び知識と才覚で這い上がっていく過程は、まさに人間ドラマの王道と言えるでしょう。
圧倒的な知性で困難を切り抜ける主人公の魅力
エウメネスの最大の魅力は、その卓越した知性と観察力です。彼は武力に頼るのではなく、状況を的確に分析し、相手の心理を読み、知恵と機転で危機を乗り越えていきます。
幼少期から書物が好きで地理、歴史、言語、数学など幅広い知識を身につけたエウメネスは、どんな困難な状況に置かれても、冷静に状況を分析し、最善の手を打ちます。時には敵を欺き、時には交渉で味方を増やし、時には大胆な策略で窮地を脱する彼の姿は、読者に知的興奮を与えてくれます。
少年時代を過ごしたボアの村でも、村人は何かを得たいのならその対価として自分が何の役に立つのか、その対価を村人のために差し出せ、という教えで、彼は「自分はヘロドトスを教える。」といい、村で暮らすために村人にギリシアの知識を教え、村に受け入れられます。
そしてその知略によって最終的にボアの村を救うことになるのですが、結局その代償として村を出ていかざるを得なくなります。
その後もマケドニア軍に包囲されたカルディアの町に入るためにエウメネスがとった知略により、フィリッポス2世は彼を高く評価し、マケドニアに誘うことになります。つまりフィリッポス2世が評価したのはエウメネスの状況分析力の高さと、それに基づいて最適解を見出し行動する知恵と機転です。
岩明均の描くエウメネスは、決して完璧な超人ではありません。時には失敗し、時には苦悩し、時には感情に流されることもあります。しかし、そうした人間らしさを持ちながらも、最終的には知性で道を切り開いていく姿が、多くの読者を魅了してやみません。
歴史の「空白」を埋める想像力
この物語の魅力は、「謎」とされていたエウメネスの前半生をこのような創作で埋めていき、「なぜエウメネスはギリシア人(本作では実はスキタイ人となっていますが)でありながらマケドニア王に仕えることになったのか」「なぜ彼は書記官という地位でありながら、大きな影響力を持つことができたのか」といった疑問に対して、説得力のある答えを提示しています。
さらに創作部分としてヘファイステオンとアレクサンドロスは実は同一人物でアレクサンドロスは二重人格という大胆な設定にしています。こうした大胆な設定も、後の世では英雄といわれ世界の半分を支配したといわれるアレクサンドロスの心の闇を作り出して物語に史実以上の深みを与えています。実際に物語ではアレクサンドロスは戦の天才ともいえる行動力を戦場で見せるのですが、非常に繊細でどこか危なっかしい面をもつ若者として描かれています。
こうした「空白を埋める想像力」こそが、「ヒストリエ」を単なる歴史の再現ではなく、創造的な歴史フィクションとして成立させているのです。史実という骨格に、岩明均の想像力という肉付けがなされることで、エウメネス、そしてアレクサンドロスという人物が立体的に浮かび上がってきます。私たち読者は、歴史的事実を学びながら、同時に一人の人間の物語として「ヒストリエ」を楽しむことができるのです。
完結を待ち望む読者たち
2006年ごろから休載が目立つようになっているという状況ではありますが、だからこそ新しい話が掲載されるたびに、読者の期待と興奮は高まります。長期連載ゆえの苦労もあるでしょうが、それでも読者は、エウメネスの物語の続きを心待ちにしています。
物語は、エウメネスがアレクサンドロス大王と出会い、歴史の表舞台に立つ段階へと進んでいます。これから描かれるであろう、アレクサンドロスの東方遠征、そしてその後のディアドコイ戦争での活躍は、まさに「ヒストリエ」のクライマックスとなるはずです。
岩明均という稀代の漫画家が、長年温めてきた構想を、一つ一つ丁寧に形にしていく過程そのものが、「ヒストリエ」という作品の価値を高めています。完結までにはまだ時間がかかるかもしれませんが、それだけに完結した時の感動は計り知れないものになるでしょう。
まとめ
なかなかマンガで描かれることが希少な時代の歴史漫画ではありますが、非常に面白い時代背景の作品でもあります。なかなか誰も手を付けないようなところで、精緻な時代考証、魅力的な主人公、複雑な人間ドラマを織りなしており、稀有な作品だと思います。
まだ読んだことのない方は、ぜひ第1巻から手に取ってみてください。古代ギリシアという遠い時代の物語でありながら、そこには普遍的な人間の姿が描かれています。そして一度読み始めたら、きっとあなたもエウメネスの知的な冒険に魅了されることでしょう。
私は『寄生獣』の終わり方は、非常にきれいな完璧な終わり方をしたと思っています。
同じように綺麗に完結していただければありがたいなと思います。
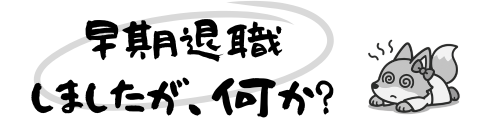
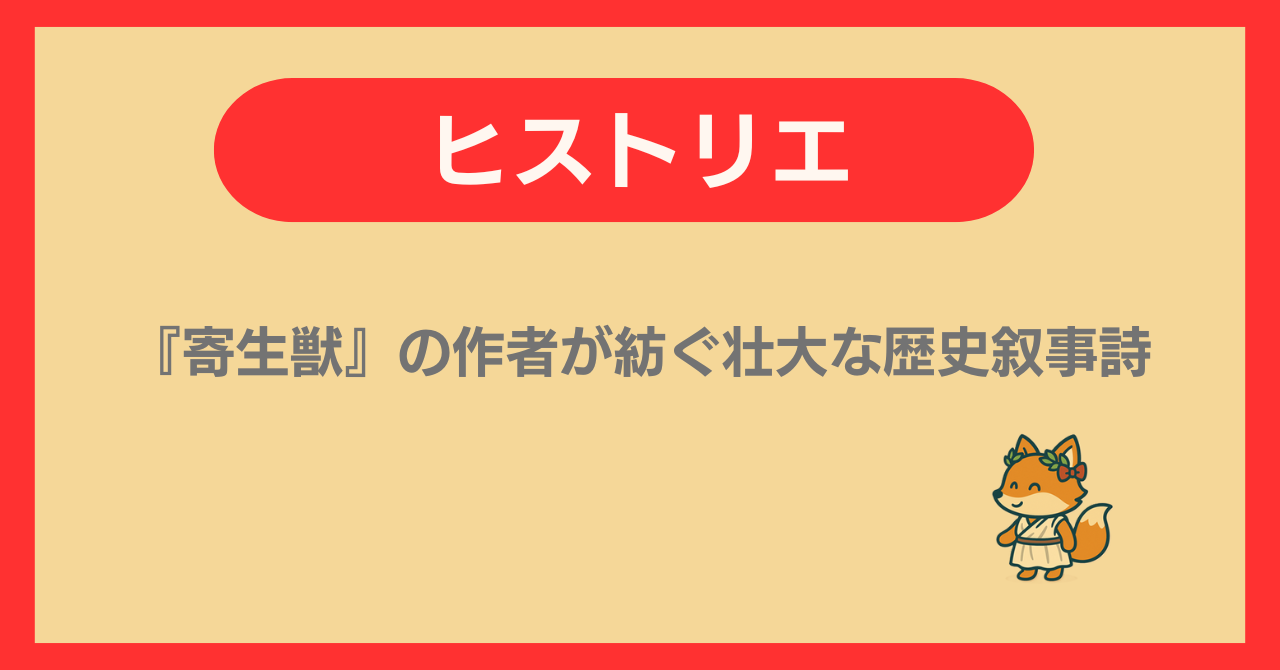
コメント