早期退職という選択肢を真剣に考えているあなたにとって、投資による資産形成は単なる選択肢ではなく、必須のスキルです。会社員としての安定した収入がなくなった後の人生を、経済的な不安なく過ごすためには、給与以外の収入源、つまり資産からの収益を確保することが不可欠だからです。
多くの人が「早期退職したい」と思いながらも実現できない最大の理由は、経済的な不安です。しかし、適切な投資知識を身につけ、計画的に資産を形成していけば、早期退職は決して夢物語ではありません。本記事では、早期退職を目指す方が知っておくべき投資の基礎知識と、具体的な資産形成戦略についてお伝えします。
こちらの内容は「早期退職のロードマップ」の退職前にすることの7項目目に挙げている部分です。すなわち早期退職のための経済的基盤の準備に該当することですので、まずはしっかりと目標をもって準備をしましょう。

早期退職に必要な資産額を知る
投資を始める前に、まず自分が早期退職するために必要な資産額を明確にすることが重要です。これは投資の目標設定の第一歩となります。
一般的に、早期退職後の生活資金を計算する際には「4パーセントルール」という考え方が参考になります。
これは資産の4%を取り崩しながら、インデックスファンドなどで投資を継続していけば、資産が目減りすることなく半永久的に資産を維持し続けることができるという、米国のトリニティ大学での研究結果を根拠とした考え方ですが、そうなると月25万円、年間300万円の生活費が必要になるという条件での必要資産額は、75百万円となります。つまり年間生活費の25倍が必要資産額という計算です。
しかしこれはあくまでも、ほかに収入なく、ただ資産を取り崩すだけという前提ですので、月にいくらかの収入があったり、年間生活費をもう少し抑えることができる、ということであればこの75百万円はどんどん下げることができます。絶対に75百万円が必要ということではなく、あくまでもベースとなる考え方と理解してください。つまり75百万円あれば、ほぼ何もしなくても月25万円の生活は維持できる可能性が高いというだけのことです。75百万円も貯めるのは無理、すなわち早期退職は無理、と考えてしまうのは早計が過ぎます。
しかも必ずしも資産残高を減らさないで維持していく、ということが絶対の目標ではありませんから、この部分も誤解のないようにしてください。月の収入額、支出額、資産の運用成績などで必要な資産の金額は変動しますし、必ずしも資産残高を維持し続ける必要もないのですから。
また、退職金や企業年金、将来の公的年金なども考慮に入れる必要があります。50歳で早期退職し、65歳から年金を受け取る場合、15年間を資産と収入で乗り切る必要があります。この「年金受給までの空白期間」をどう埋めるかが、早期退職計画の核心部分です。
ただし重要なのは、楽観的すぎる見積もりをしないことです。医療費、介護費用、インフレ、予想外の支出なども考慮に入れ、余裕を持った資産額を目標とすべきです。
投資が早期退職に不可欠な理由
なぜ早期退職に投資が不可欠なのでしょうか。それは、銀行預金だけでは十分な資産を形成できないからです。
仮に毎月10万円を30年間貯金した場合、金利がほぼゼロの現在では、総額は3,600万円にしかなりません。一方、同じ金額を年率5パーセントで運用できれば、約8,300万円になります。その差は実に4,700万円です。この違いが、早期退職できるかどうかを左右するのです。
さらに、早期退職後も資産を運用し続けることで、資産寿命を延ばすことができます。退職後に資産を銀行預金に置いておくだけでは、取り崩すだけの一方通行になりますが、適切に運用することで、資産を維持しながら生活費を賄うことが可能になります。
また、インフレから資産を守るためにも投資は重要です。現金の価値は時間とともに目減りしていきますが、株式などの資産はインフレに対応して価値が上昇する傾向があります。30年、40年という長期にわたる退職後の人生を考えると、インフレ対策は避けて通れません。
投資による配当金や分配金は、退職後の定期的な収入源にもなります。月々10万円の配当収入があれば、生活費の大きな部分を賄えます。これは給与に代わる「不労所得」として、早期退職後の生活を支える柱となるのです。
早期退職を目指す人の投資戦略
早期退職を目指す場合、一般的な投資とは少し異なる戦略が必要です。特に重要なのは、「資産形成期」と「資産活用期」を明確に区別して考えることです。
退職までの期間は「資産形成期」です。この時期の目標は、できるだけ多くの資産を積み上げることです。したがって、リスクを取って成長性の高い資産に投資することが基本戦略となります。株式中心のポートフォリオで、積極的に資産を増やすことを目指しましょう。
具体的には、全世界株式インデックスファンドや米国株式インデックスファンドなど、長期的な成長が期待できる商品を中心に積立投資を行います。退職まで10年以上あるなら、短期的な価格変動は気にせず、ひたすら積み立て続けることが重要です。
月々の投資額は、できる限り多くすることが望ましいです。生活費を切り詰め、固定費を削減し、可能であれば副業で収入を増やし、その分を投資に回しましょう。早期退職という目標のために、今は我慢する時期だと考えることが大切です。
退職の5年前くらいからは、徐々にポートフォリオを調整していきます。株式の比率を下げ、債券や現金の比率を上げることで、退職時に暴落が起きても影響を最小限に抑えられるようにします。これを「グライドパス戦略」と呼びます。
退職後は「資産活用期」に入ります。この時期の目標は、資産を維持しながら安定した収入を得ることです。株式と債券のバランスを取ったポートフォリオに調整し、年間4パーセント程度の取り崩しで生活費を賄います。あまりにリスクを取りすぎると、暴落時に資産が大きく減少して生活が破綻する危険があります。
早期退職前に実践すべき投資方法
早期退職を目指す方が今すぐ実践すべき投資方法について、具体的にご紹介します。
まず最優先で活用すべきは、NISA制度です。2024年に新しくなったNISA制度では、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計で年間360万円まで投資でき、生涯投資枠は1,800万円です。運用益が非課税になるため、早期退職を目指すなら必ず活用すべき制度です。
つみたて投資枠では、全世界株式インデックスファンドや米国株式インデックスファンドを毎月積み立てます。月10万円を10年間積み立てれば、元本だけで1,200万円、年率5パーセントで運用できれば約1,550万円になります。
成長投資枠は、ボーナスなどまとまった資金がある時に活用します。つみたて投資枠と同様の商品に投資してもよいですし、配当金の高い個別株やETFを購入して、将来の配当収入を確保する戦略も有効です。
iDeCoも活用すべきですが、60歳まで引き出せないという制約があるため、早期退職の年齢によっては使いにくい面もあります。50代で退職を考えているなら積極的に活用し、40代前半での退職を考えているなら、NISA優先で考えた方がよいでしょう。
特定口座での投資も並行して行います。NISA枠を使い切った後は、特定口座で投資を続けましょう。こちらは運用益に約20パーセントの税金がかかりますが、それでも預金よりはるかに効率的です。
早期退職を目指す人に特におすすめなのが、高配当株投資です。配当利回り3パーセントから4パーセント程度の優良企業の株式を複数保有することで、退職後の安定した配当収入を確保できます。5,000万円を配当利回り4パーセントの株式で運用すれば、年間200万円の配当収入となり、生活費の大部分を賄えます。
早期退職後の資産運用と取り崩し戦略
早期退職を実現した後の資産運用も重要です。退職時に築いた資産を、いかに長持ちさせるかが鍵となります。
基本的な戦略は「4パーセントルール」に基づいた取り崩しです。総資産の4パーセントを年間の生活費として取り崩していけば、統計的には資産が枯渇する可能性は低いとされています。月25万円の生活費なら、年間300万円、総資産7,500万円の4パーセントに相当します。
ただし、機械的に4パーセントを取り崩すのではなく、市場の状況に応じて柔軟に対応することも大切です。株式市場が好調で資産が増えている年は、5パーセント取り崩しても問題ありません。逆に暴落した年は、3パーセント程度に抑えるなど、生活費を調整する余地を持っておくことが望ましいです。
退職後のポートフォリオは、株式60パーセント、債券30パーセント、現金10パーセント程度が一つの目安です。株式の比率が高すぎると暴落時のダメージが大きく、低すぎると資産の成長が見込めません。年齢が上がるにつれて、徐々に債券の比率を上げていくことも検討しましょう。
取り崩しの順序も重要です。基本的には、税金のかかる特定口座の資産から取り崩し、NISA口座の資産はできるだけ長く保有し続けることで、非課税メリットを最大限活用できます。
また、退職後も少額の収入を得ることで、資産の取り崩しペースを大幅に遅らせることができます。週2日程度のパートタイム労働で月5万円稼げば、年間60万円の取り崩しを減らせます。これは資産寿命を大きく延ばす効果があります。
投資で失敗しないための早期退職者特有の注意点
早期退職を目指す人が投資で失敗しないために、特に注意すべき点があります。
まず、退職直前の暴落リスクです。退職の1年前に株式市場が大暴落し、資産が半分になってしまったら、退職計画は大幅に狂います。これを「シーケンスリスク」と呼びます。対策としては、退職の数年前から徐々に安全資産の比率を高め、退職直前には少なくとも3年分の生活費を現金や債券で確保しておくことが重要です。
次に、過度なリスクを取らないことです。「早く資産を増やしたい」という焦りから、個別株の集中投資や仮想通貨、FXなどハイリスクな投資に手を出すと、失敗した時の損失が取り返しのつかないものになります。早期退職のための投資は、着実に資産を増やすことが目的であり、一攫千金を狙うものではありません。
生活水準の上昇にも注意が必要です。投資で資産が増えてくると、つい生活水準を上げたくなりますが、それでは早期退職の時期が遠のきます。退職までは節約を続け、退職後も質素な生活を維持することが、早期退職成功の秘訣です。
また、投資の勉強を怠らないことも重要です。マーケットの状況、税制の変更、新しい投資商品など、常に情報をアップデートし続けることで、より効率的な資産形成が可能になります。ただし、情報に振り回されすぎないよう、基本方針は堅持することも大切です。
最後に、家族の理解と協力も不可欠です。早期退職は人生の大きな決断であり、家族全員が納得していなければ成功しません。投資方針や退職後の生活設計について、家族でよく話し合い、共通理解を持つことが重要です。
まとめ – 計画的な投資で早期退職の夢を実現する
早期退職は、適切な投資戦略と十分な準備があれば、決して不可能な夢ではありません。重要なのは、できるだけ早く投資を始め、長期間にわたって積み立てを続けることです。
今から10年後、15年後の早期退職を目指すなら、今日から行動を始めるべきです。NISA口座を開設し、インデックスファンドの積立を始め、支出を見直して投資額を増やしましょう。そして投資の知識を深め、市場の変動に動じない精神力を養いましょう。
証券口座の開設であれば、ネット証券がおすすめです。
SBI証券、楽天証券が使いやすくてよいと思います。またマネックス証券は銘柄スカウターの機能が充実していますので、こちらの証券口座もおすすめです。
早期退職という目標は、あなたの人生に明確な方向性を与えてくれます。その目標に向かって投資を続けることで、知らず知らずのうちに大きな資産が形成されていきます。
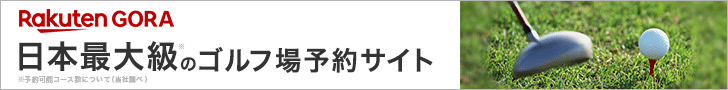

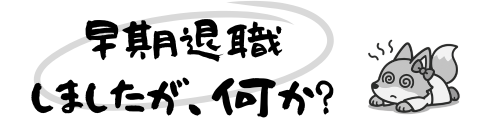
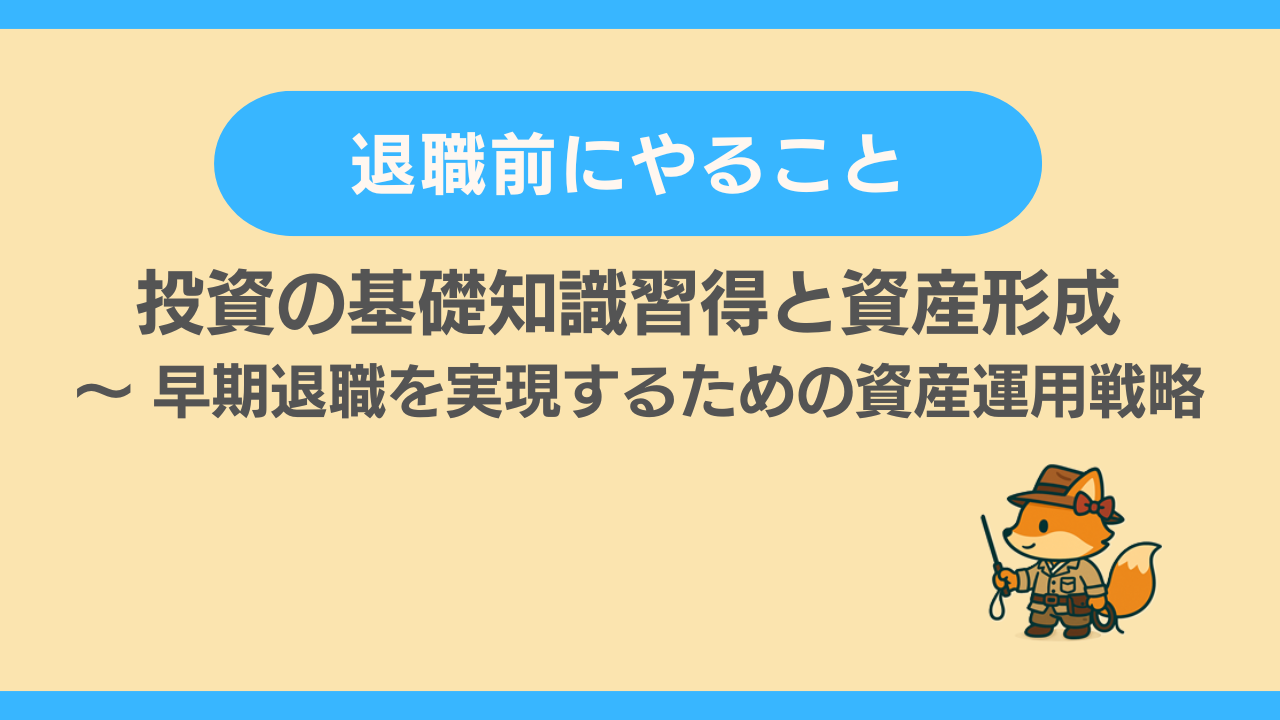
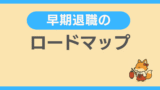
コメント